
研究員・アナリスト紹介
Researcher Profile

XR・立体映像
小磯 諒太
コイソ・リョウタ
2019年にKDDI入社。運用部門にて運用設備リソース管理業務を経て、KDDI総合研究所にてXR関連技術の研究に従事。自由視点映像や立体映像ホログラフィなどの研究発表や展示会出展を推進。2024~2025年にはスタンフォード大学客員研究員として、大型直視型ホログラフィックディスプレイやAIベースの写実的なホログラフィ計算技術の研究開発に従事。現在は米国での経験を基に、立体映像技術の高度化に向けた研究を推進。2020年映像情報メディア学会鈴本記念奨励賞、2023年同学会映像情報メディア未来賞、2024年電子情報通信学会学術奨励賞を受賞。
自然言語処理・対話システム
古舞 千暁
フルマイ・カズアキ
2020年KDDI入社後、設備の自動監視システムに関する開発業務を経て、2021年からKDDI総合研究所で、主に対話システムに関する自然言語処理技術の研究に従事。現在は、目的タスクの達成性能を損なわずに生成AIのハルシネーション(事実と異なる情報が生成される現象)を抑制する技術の研究を担当。2022年~2024年にスタンフォード大学との共同研究に従事し、自然言語処理のトップカンファレンスの一つであるEMNLP2024にて採択論文を発表。その研究成果を基に様々なタスクに適応可能かつ信頼性の高い対話型AIエージェントを開発し、KDDI事業への商用導入を進めている。
量子コンピューティング
古澤 瞬
フルサワ・シュン
大学では機械学習の理論および応用を専門とする研究室に所属し、スマートフォン依存の実態解析に関する共同研究に参加。2023年にKDDIへ入社し、モバイル端末の通信品質管理業務を担当。2024年からKDDI総合研究所で量子コンピューティングの研究に従事。現在は、無線通信分野における組合せ最適化問題に対する量子アニーリングなどの量子技術を用いた手法の開発に加え、大規模言語モデルなどの生成AIを活用した量子プログラミングの研究にも取り組んでいる。
拡散モデル
大矢 友貴
オオヤ・トモキ
2023年KDDIに入社後、通信エリア品質改善業務を経て、2024年からKDDI総合研究所で、画像編集、音声編集やテーブルデータ生成の拡散モデルの研究に従事。加えて、最先端のデータ生成技術調査も実施し、最新の技術動向の把握や応用可能性の評価を行っている。現在は、関連部署に対するヒアリングを通じてニーズを把握した上で、生成AIを活用した応用研究に取り組んでおり、具体的には、音声生成向けに開発された拡散モデルを用いて、人の指示に基づく音声編集の新たな手法の考案や、複雑な構造を持つテーブルデータに対して高精度にデータを生成できる新規のアルゴリズムの研究を進めている。
モバイルネットワーク・MEC・月地球通信等の通信システム
城 哲
ジョウ・テツ
2012年にKDDIに入社後、携帯向け国際通信の監視・運用や携帯向け音声通話システムの開発業務を経て、2019年からKDDI総合研究所に出向。モバイルネットワークやMEC、IoT等をキーワードとして通信の効率化や品質向上のための通信システムのアーキテクチャや制御方式、通信方式に関する研究に取り組んできた。2023年からは、モバイルネットワークのU-Plane共通化を通じたC-Plane処理の簡略化や、月地球間通信のための新たな通信プロトコルスタックの検討に関する研究に従事している。最近飼い始めたハムスターが、掃除のたびに壊される巣を、淡々と何度も何度も作り直すひたむきな姿に、私も見て学ぶべきだと感じております。
無線ネットワークアーキテクチャ・マネジメント
塚本 優
ツカモト・ユウ
2016年に入社後、運用部門にて法人向けネットワークのシステムエンジニア業務の経験を経て、2017年からKDDI総合研究所で、無線アクセスネットワーク(RAN)のアーキテクチャ及びマネジメントに関する研究に従事。5Gの高度化時代に向けて、RANの仮想化やスライシング技術を活用し、ユーザの要求に応じた適応的なRANアーキテクチャに関する研究を担当。現在は6Gに向けて、高い通信品質をスケーラブルに提供可能なRANを目指して、セルフリー方式のための新しいRANアーキテクチャや、AI/MLを活用したRANの最適化制御の研究を進めている。2019年に電子情報通信学会の通信方式研究会奨励賞、2020年に学術奨励賞を受賞。
映像メディア・XR
渡邊 良亮
ワタナベ・リョウスケ
2016年にKDDI入社後、運用業務を経て、2017年からKDDI総合研究所でXR関連の研究に従事。研究所配属後は、自由視点映像や立体映像に関する研究発表やKDDIの事業部と連携した実証などを推進。その後、2021年~2024年に南カリフォルニア大学との共同研究推進のため渡米。同大学の客員研究員として、グラフ信号処理を活用した3D点群データの品質改善や品質評価技術の研究開発を推進。現在は、米国赴任中に培った専門性を活かしながら3D空間再現技術に関する研究に従事。2023年には、国際会議IEEE ICASSP 2023で自身の発表が「Top 3% Paper Recognition」に認定、国際会議IEEE ICIP 2023で行われた3D点群データの品質評価に関するGrand Challengeで優勝。2024年には国際会議IEEE ICIP 2024にて「Best Paper Award」を受賞。博士(情報科学)。
光ファイバー情報通信
エルソン ダニエル
エルソン・ダニエル
Born in the UK. Completed a undergraduate degree at Imperial College London in Physics, before moving to UCL (University College London), to complete a PhD in optical fibre communications. During which I had a 4-month internship at NICT looking at using multicore fibres. After graduation I moved to the Photonic Transport Network Laboratory at KDDI Research in 2019 to continue this research. Now I focus on novel transmission schemes and future options for fibre optic based networks.
トラスト・サイバー攻撃対策
三本 知明
ミモト・トモアキ
2014年KDDI入社後、運用部門でシステム開発業務の経験を経て、2015年からKDDI研究所(当時)にてセキュリティ・プライバシの研究開発業務に従事。その後2020年から2023年まで国際電気通信基礎技術研究所にてプライバシ強化技術に関する共同研究の立ち上げを主導。2023年から再びKDDI総合研究所に配属となり、トラストおよびサイバー攻撃対策の研究に取り組む。現在は主に信頼性の高いサイバー脅威情報の収集や、それらを活用したサイバー攻撃対策に関する研究を担当している。東洋大学非常勤講師および大阪大学招へい准教授として講義活動にも従事。博士(工学)。
Beyond 5G/6G時代に向けた無線通信方式
神渡 俊介
カミワタリ・シュンスケ
2020年KDDI入社後、運用部門でのネットワーク設備の保守・運用業務を経て、2021年KDDI総合研究所に出向、Beyond 5G/6G時代に向けた無線通信方式の研究/標準化活動に従事。現在は、エリア内の基地局を協調動作させることでユーザの位置によらず最適な通信品質を提供するセルフリーネットワークの研究に従事。特に、5Gより活用されているミリ波帯をはじめとした高周波数帯域を用いたセルフリーネットワークに適したビームフォーミング方式の実現に向けた研究を行っている。関連する国内外の学会活動に加えて、国際標準化団体の3GPPにおいても研究成果の規格化を目指し活動している。2024年に電子情報通信学会「学術奨励賞」を受賞。
韓国の通信政策・市場戦略
キム ダジョン
キム・ダジョン
韓国出身。2016年KDDI Koreaに入社し、韓国の通信市場や通信関連市場についての政策や市場戦略の調査に携わる。政策では、端末補助金規制、周波数オークション、ユニバーサルサービス、GAFAを始めとするプラットフォーム規制、個人情報保護法などの調査を行い、市場戦略の調査では、韓国通信事業者の5G料金プランやサービス、AIやUAM等のビジネスモデル、SDGs等を調査していた。その後、2022年にKDDI総合研究所入社、通信市場・通信関連政策に加え、韓国でのリテールテック、Eコマース、AI、教育、2030年の未来像を踏まえた食生活や働き方など、KDDIの戦略分野に幅を広げ調査している。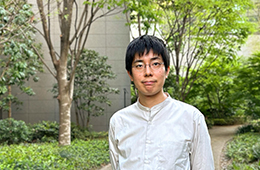
デザインリサーチ・UIUXデザイン
杉浦 彰彦
スギウラ・アキヒコ
美術大学でセノグラフィーを学び、社会人を経て修士を機に渡独。修了後はドイツにてUXリサーチ、UIUXデザイン、ローカライゼーションなど、デジタルプロダクト関連のデザインに従事してきた。2023年にKDDI総合研究所入社後は、主にデザインリサーチに関する研究を行っている。特に、オープンイノベーションの下地として、専門知識や暗黙知を(現場の必要や状況に沿った形で)どう伝達・集約・蓄積していくか?といった問題に、様々な実践活動とツールの開発を通して取り組んでいる。
脳神経科学
杉崎 えり子
スギサキ・エリコ
約10年間の民間企業での勤務を経て、博士課程では実験動物を用いた細胞・システムレベルでの記憶のメカニズムの解明を行った。2023年にKDDI総合研究所に入社し、グループメンバーとともにヒトを対象とした脳神経科学とAIを組み合わせた研究に従事している。特に、生体情報(脳波、心拍など)やスマホログから精神状態を予測し、適切な視聴覚刺激を選定・提示して場面に応じた最適な認知能力の発揮を可能にする研究に取り組んでいる。また、日常生活の一部となっているゲームプレイ内(非現実空間)の行動特性やスマホログに注目して精神疾患傾向を早期に把握する技術開発への貢献を目指している。
6G時代のネットワークアーキテクチャ・マネジメント
伊神 皓生
イカミ・アキオ
2013年にKDDI入社後、5G向けアクセスネットワークの企画及び伝送機器(WDM/SW/Router)の開発業務に従事。2018年KDDI総合研究所に配属、無線分野の研究開発に従事し現在に至る。KDDI総合研究所では、ダイナミック周波数共用の研究の後、現在は6Gへ向けたRANアーキテクチャ・マネジメントに関わる研究を担当。RAN視点での無線信号処理機能の制御、伝送区間を考慮した次世代RANアーキテクチャ、共通仮想基盤上でのRANとコアネットワークの連携といったネットワーク全体を俯瞰した検討から、数理最適化・AI/ML・量子技術のRAN制御への応用まで幅広い技術を用いた研究を進めている。6Gへ向けたO-RANでの標準化活動にも従事。2020年に電子情報通信学会から「学術奨励賞」を、2022年に国際会議IEEE VTC2022-Fallにて「Best paper award」を受賞。
ヘルスケア
永田 雅俊
ナガタ・マサトシ
KDDI入社後、インターネット設備の運用・保守業務を経て、2015年からKDDI総合研究所でヘルスケア領域の研究開発に従事。健康推進のための行動変容研究に携わる過程で、人を対象とした研究実験倫理に関する所内の規程づくりを行い、倫理審査のための仕組みを整備。現在は、ゲノム・エピゲノムデータ等の生体情報を用いた、疾病予防や健康増進に関する研究を担当。健康関連データの解析を通じて、健康寿命の延伸のために一人ひとりに最適なライフスタイルの提案ができることを目指し、倫理やセキュリティにも留意しながら研究を進めています。情報処理安全確保支援士、統計検定準1級(2022年最優秀成績賞受賞)。
情報セキュリティ・暗号
成定 真太郎
ナリサダ・シンタロウ
2018年KDDIに入社後、運用本部でのシステム開発業務を経て、2019年からKDDI総合研究所で耐量子計算機暗号(量子コンピュータによる攻撃に耐性のある暗号方式)や高機能暗号、AIセキュリティに関する研究に従事。現在は、耐量子計算機暗号の一種である符号暗号に関する研究を行っている。符号暗号を実際に解読して、その安全性を詳細に評価することにより、安全性と速さを両立する次世代暗号方式の実現に貢献したいと考えている。これまで、Decoding Challenge(符号暗号の暗号解読コンテスト)での世界記録9回達成。CRYPTREC(Cryptography Research and Evaluation Committees)委員として我が国の暗号政策に貢献(2023年度-)。
モバイルコア
鈴木 理基
スズキ・マサキ
シンクタンクでエンジニアを経験後、博士号を取得しKDDIに入社。KDDI総合研究所では、モバイルコアに関連する研究開発/標準化に従事し、近年ではETSI ISG MECにてMEC federationに関わるスタディおよび仕様作成のワークアイテムをラポータとして牽引しました。更に、その社会実装に関するホワイトペーパーをエディタとして完成させ、IEEEなどの国際学術会議やEU DG CONNECT主催のイベント等で講演を行い、規格普及に寄与しています。 2022年からはモバイルコアの研究開発/国際標準化を担当するチームのリーダーを務め、6Gの新たなモバイルコアのアーキテクチャ実現を目指して、高性能・レジリエント・カスタマイズを主軸にした要素技術の研究開発/標準化を進めています。 2023年に日本ITU協会賞奨励賞を受賞。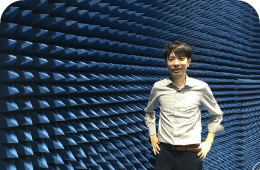
フォトニクス
石村 昇太
イシムラ・ショウタ
2015年KDDI入社後、auひかり保守運用業務を経て、2016年からKDDI総合研究所で、光ファイバー無線・マイクロ波フォトニクスの研究に従事。現在は、非線形光学、光デバイス、光コンピューティングなどの研究に従事。2014年光通信システム研究会「論文賞」、2019年電子情報通信学会「学術奨励賞」などを受賞。国際学会European Conference on Optical Communication(ECOC)、国際学会Asia Communications and Photonics Conference(ACP)、国際学会Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO-PR)、レーザ・量子エレクトロニクス研究専門委員会などの専門委員を歴任。博士(工学)。
SBOM(ソフトウェア部品表)・デジタルID認証
小島 孝夫
コジマ・タカオ
インターネットプロバイダやシステムインテグレータでの25年にわたるインターネット業務経験の中で、システムエンジニアとして官公庁・金融向けエンドポイントセキュリティを設計・展開。情報セキュリティ大学院大学で博士号(情報学)を取得後、情報セキュリティの専門家としてKDDIに入社し、米国シリコンバレーに駐在。OpenID FoundationやFIDO Allianceといったグローバルな標準化団体での活動を通じて得た国内外セキュリティ専門家との豊富なソーシャルネットワークを活かして、「au ID」のオープンアーキテクチャ化・フィッシング対策を開発。研究所では通信分野におけるSBOM(ソフトウェア部品表)などのサプライチェーンセキュリティの研究に従事。米ACM会員。
シンクタンク・産業・デジタルマーケティングリサーチ
劉 亜菲
リュウ・アヒ
中国出身。北海道大学国際広報メディア・観光学院博士課程修了。博士(学術)。専門分野は、ソーシャルメディア、ネットオピニオンリーダー、ネット世論形成。KDDI総合研究所入社後、中国OTT産業・デジタルマーケティングに関する研究調査を担当。近年は、インフルエンサーマーケティング、デジタルコンテンツ、ECビジネス(ライブコマース、ソーシャル共同購買)を中心とした調査・戦略検討・事業化支援に従事。日本マーケティング学会カンファレンス、情報通信学会全国大会などで研究発表を実施。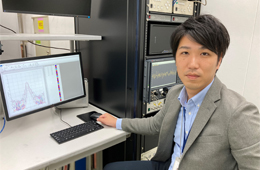
電波伝搬
伊藤 智史
イトウ・サトシ
2015年KDDI入社後、運用部門でメールサーバーの保守運用業務の経験を経て、2016年にKDDI総合研究所に配属。その後、2021年からKDDIでRAN機能開発の企画業務に従事したのち、2022年から再びKDDI総合研究所に配属となり現在に至る。KDDI総合研究所では、移動通信システムの研究開発に従事し、これまで5G導入に向けたミリ波帯電波伝搬特性の解明やモデル化に関する研究を実施。現在はB5G/6Gに向けたテラヘルツ帯等の新たな周波数帯に関する研究や機械学習による電波伝搬特性のモデル化などの研究を担当。専門研究は電波伝搬で、アンテナ・伝搬研究専門委員会に参加し、2021年に電子情報通信学会「学術奨励賞」を受賞。
コネクティッドネットワーク・ネットワーク運用自動化
河崎 純一
カワサキ・ジュンイチ
入社後、国際通信の監視・運用業務を経て、2016年からKDDI総合研究所で、現場経験を生かし運用自動化の研究開発に従事。現在は、自動化のトリガーとなる通信障害検知や分析に、AI技術を活用することで、ネットワーク運用を効率化・高度化するための研究を担当しています。専門研究は、運用管理・自動化で、国内外の関連学会において発表すると共に、国際標準化団体ETSI ZSMにおいても活動し、研究で得られた成果の規格化提案も行っています。
光ファイバー無線
二村 真司
ニムラ・シンジ
KDDI入社後、au基地局の運用業務、通信エリア品質改善業務を経て、2021年からKDDI総合研究所で、光ファイバー無線を中心とした光伝送技術に関する研究に従事。現在はBeyond 5G・6G時代に求められる高速大容量な無線通信を支える技術として、複数の基地局向けに無線信号を多重して伝送する方式を担当し、無線と光を融合させた新たなネットワーク構成の実現に向けた研究を行っている。専門研究は光アクセス伝送技術で、関連する国内外の学会にて活動中。
循環経済
経沢 正邦
ツネザワ・マサクニ
大学でアンテナ・電波伝搬などの通信工学を専攻し修士課程を修了。2017年にKDDIへ入社。社内業務効率化のシステム開発業務を経て、2018年からKDDI総合研究所で研究開発計画の立案・管理・評価の取りまとめなどの企画業務などに従事。同業務の中で取り組むべき研究領域の調査・プロジェクト化に携わり、新たに立ち上げた循環経済の研究プロジェクトに2021年から現在まで取り組む。2022年から業務の傍らで東京大学工学系研究科博士課程に入学し、ライフサイクル工学について学んでいる。サステナブルな社会の実現を目指し、これまでにない資源循環システムや環境影響評価手法、ビジネス設計方法論の研究開発などを進めている。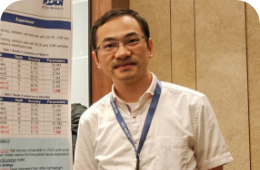
マルチモーダル・モデリング
王 亜楠
オウ・アナン
2017年KDDIに入社後、運用業務を経て、2018年からKDDI総合研究所で、マルチモーダルモデルの研究に従事。現在、人間のように目の前の状況を的確に説明ができて、目的タスクの達成に必要とするプランニングや推論ができるエージェント型マルチモーダルシステムの研究を担当。2020年~2023年にスタンフォード大学で客員研究員として共同研究に従事、視覚常識推論(VCR)タスクで世界1位を達成(*2022年4月時点)、ICCV2023で採択論文を発表。博士(工学)。
映像符号化
河村 圭
カワムラ・ケイ
大学で博士課程を修了後KDDI入社。2010年からKDDI研究所(当時)で、映像符号化方式の研究と、その国際標準化活動に従事。その後、KDDI企画部門にて、STB(Set Top Box)開発や機能拡張、映像伝送などの経験を積む。現在は、最新の映像符号化方式であるVVC(Versatile Video Coding)実用化に向けたエンコード方式の研究開発や、VVC拡張方式の標準化活動を牽引。さらに、グループメンバーと共に、点群データの取得、符号化、再生に関する研究にも対象を広げています。2013年度 電子情報通信学会「学術奨励賞」、2019年映像メディア学会「次世代テレビ技術賞」、2020年情報規格調査会「標準化貢献賞」を受賞。博士(国際情報通信学)。
シンクタンク・海外市場・政策リサーチ
加藤 尚徳
カトウ・ナオノリ
通信系シンクタンクでの研究員を経て、KDDIに入社。現在は、KDDI総合研究所で、情報法制(プライバシー・個人情報等)を中心とした法制度や技術の調査・研究・コンサル業務に従事しています。2019年3月「日米欧の自動走行に関する政策動向比較と今後の我が国の方向性に関する一考察」で、情報処理学会「山下記念研究賞」を受賞。2019年12月、AIの開発原則や法規制の動向調査に対して、IDF優秀若手研究者として表彰される。総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻単位取得満期退学、修士(情報学)、一般社団法人次世代基盤政策研究所理事・事務局長、放送大学客員准教授、理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員、神奈川大学非常勤講師、慶應義塾大学SFC研究所上席所員。